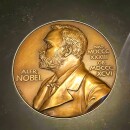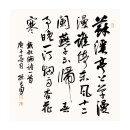日本が「毎年」ノーベル賞を獲得する四大理由―米国華字メディア
拡大
米国に拠点を置く華字メディアのチャイナ・デジタル・タイムズは、21世紀になってから日本人のノーベル賞受賞者は平均して毎年ほぼ1人として、その理由を分析する記事を発表した。
先ごろ、2025年の生理学・医学賞を坂口志文氏が、同化学賞を北川進氏が受賞した。米国に拠点を置く華字メディアのチャイナ・デジタル・タイムズは今年の日本人2人のノーベル賞受賞を受け、「21世紀に入ってからわずか25年で、日本はノーベル米国籍になった3人を含めてノーベル自然科学賞の受賞者を22人輩出している。平均すれば毎年1人が誕生している」として、その理由には4点があると主張する記事を発表した。以下は、同記事を再構成した文章だ。
教育が科学研究の火種を普通の人々の心にまいた
ノーベル賞は単独の天才によって得られるのではなく、国民教育という土壌から自然に咲いた「花」だ。日本では、基礎教育の厳密さと普及度が科学研究のための堅固な基盤を築いている。
日本の基礎教育は水準が高く小学校から高校まで広く行き渡り、「エリート教育」と「一般教育」の明確な区別はほとんど存在しない。これにより、日本の子どもたちは均衡の取れた教育環境の中で成長でき、社会全体が人材の肥沃な土壌となる。例えば日本では、図書館が地域に広く分布し、日本人1人あたりの年間読書量は十数冊だ。子供らはこのような環境にあって、教科書の知識だけでなく、学際的な興味も育まれる。科学は決して高みにあるものではなく、日常生活と結びついている。
:貧富の差が小さく、研究の機会は誰にでもある
科学分野での飛躍的な成果には、往々にして「忍耐強い孤独」が必要だ。しかし、もし社会に貧富の格差が大きく、研究者が生活のために奔走しなければならないならば、何十年にもわたる実験に安心して没頭することは難しい。
日本の特異な点は、先進国の中でも依然として極めて低い所得格差を維持している数少ない社会の一つであることだ。このような環境では、研究の機会は出身家庭の背景ではなく、個人の努力により多く結びつく。日本の若者が研究者を志す場合、経済面の制約のために「博士課程に進めないのではないか」と心配する必要はほとんどない。学費や奨学金制度が彼らを支え、大学の研究室は受け入れてくれ、企業の研究開発部門も門戸を広く開いていることが多い。
さらに重要なのは、日本社会が研究者に対して示す敬意が、スターや巨大資本家への熱狂的な支持をはるかに上回っていることだ。日本では研究は「清貧の象徴」ではなく、品格があり人々から敬われる職業なのだ。
謙虚さと忍耐、研究を「修行」と考える
日本文化には独特の気質がある。謙虚さと忍耐を重視することだ。この気質は、研究にも深く浸透している。
外部の人々の目には、ノーベル賞受賞者は科学の頂点に立つ「巨人」に見える。しかし日本では、多くの受賞者がしばしば「私はただ運が良かっただけ」と語る。南部陽一郎氏や山中伸弥氏は、自らの成果を「偶然」と表現したことがある。これは偽善ではなく、日本の文化に根差した心構えだ。このような態度は科学研究に非常に有利だ。何度失敗しても簡単には諦めず、成果がどれほど輝かしくても自らを神格化しない。
もう一つ称賛すべき点がある。それは、日本社会は個人の英雄主義ではなく、チームワークを非常に重視することだ。日本の多くのノーベル賞級の成果は、学際的かつ機関をまたいだ協力から生まれている。「過度な個人主義による衝突」がないからこそ、科学者は協力の中で忍耐を保ち、成果をじっくりと磨き上げることができる。
科学研究は象牙の塔に引きこもらない
日本のノーベル賞受賞者のかなり割合が、研究の出発点を企業の研究開発部門に置いていた人だ。例えば白川英樹氏は、「導電性プラスチック」の研究を工場という環境の中で完成させた。東芝、日立、パナソニックといった多くの企業は、20世紀の時点で巨額の資金を投入して自社の研究所を設立し、短期的な利益だけを追求するのではなく、科学者が自由に探究できるよう支援する姿勢を示していた。
また、日本の研究者は大学の研究室と企業の研究所の間を自由に行き来でき、「身分が純粋でない」と心配する必要はない。日本では科学と産業が結びついているとの認識が非常に強く、これによって科学研究の成果が応用され、実用化されやすくなっている。
日本では教育が若者に探究する勇気を与え、社会は研究者に平等な機会を提供し、文化は研究者の忍耐と謙虚さを育み、企業と一般市民は彼らに支援を与え敬意を払う。このことこそが、日本がトップレベルの科学者を輩出し続ける真の基盤だ。(翻訳・編集/如月隼人)
関連記事
中韓は「畏敬」と「嫉妬」が交錯、ノーベル医学・生理学賞と化学賞の日本人受賞
Record China
2025/10/12
中国はなぜ自然科学分野のノーベル賞を取れないのか―オーストリア紙
Record China
2025/10/10
日本出身者の自然科学分野のノーベル賞受賞は27回、韓国はゼロ=韓国ネット「うらやましい」
Record Korea
2025/10/10
なぜ台湾は日本のようにノーベル賞が取れないのか―台湾メディア
Record China
2025/10/10
日本がまたまたノーベル賞受賞!われわれは何に注目すべきか?―中国メディア
Record China
2025/10/9
「日本はノーベル賞の数でリードも科学技術では中国に大きく後れ」=中国企業関係者の主張にネット賛否
Record China
2025/10/9