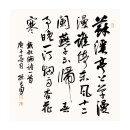アジア人労働者への門戸は閉ざされるのか、深刻化する人手不足と排外機運の広がり
拡大
日本に来る外国人労働者の大半はアジア諸国の出身。日本社会で顕在化している人手不足は少子化・高齢化を主因に今後一段と深刻化する恐れがあるが、門戸は閉ざされるのだろうか。資料写真。
筆者は今年6月の当欄で、「人口減少が進む中で地域社会を活性化するため、秩序ある外国人材受け入れが必要」と主張する団体の呼びかけを紹介した。その時点では外国人問題への注目度は高くなかったが、その後の参議院選挙と自民党総裁選では、主要な論点の一つに急浮上した。それも、どちらかといえば外国人を排除する方向で議論が展開されている。日本に来る外国人労働者の大半はアジア諸国の出身。既に日本社会で顕在化している人手不足は、少子化・高齢化を主因に今後一段と深刻化する恐れがあるが、それにもかかわらず彼らへの門戸は閉ざされるのだろうか。
外国人に否定的な空気
7月の参議院選挙では、海外マスコミから「極右」と形容される参政党が14議席を獲得して躍進した。同党のHPをみると、「教育・人づくり」「食と健康・環境安全」「国のまもり」を三つの重点政策として列記。このうち、「国のまもり」の具体的な取り組みとして「移民受け入れより、国民の就労と所得上昇を促進!」と明記しており、外国人労働者の受け入れには反対の立場だ。
10月の自民党総裁選では、党内で最右派とされ、「外国人との付き合い方をゼロベースで考える」と主張した高市早苗氏が当選した。「ゼロベース」の意味はいまひとつよく分からないが、同氏が入国管理の厳正化を主張したり、中国人観光客による奈良公園の鹿への暴力を取り上げたりしていることなどから見て、外国人に対してやや厳しいスタンスを取っていることは明らかだ。
また、ネット空間では外国人による犯罪への不安を記した投稿があふれ、私の周囲でもそうした声は聞かれる。外国人材受け入れに前向きな人たちは「外国人だからといって犯罪率が高いということは一切ない」(國松孝次・元警察庁長官)とデータに基づいて反論するが、外国人が事件を起こした場合、テレビニュースなどで容疑者を「中国国籍の…」「ベトナム出身の…」などと紹介するケースが多いことから、「外国人が増えると犯罪が多発する」という印象が広がるのだろう。いずれにしても、ここ数カ月の間で、日本社会に外国人に対する否定的な空気が広がったことは間違いない。
出生数、25年でほぼ半減
一方で、急速に進む少子化・高齢化を主因に、国内の人手不足は一段と深刻化している。東京都交通局は10月から、都営バスの全126路線のうち、19路線で206便を減便した。交通局はその理由について、バスの運行を委託している企業の乗務員不足のためと説明した。以前から地方では運転手不足で減便や路線廃止が相次いでいたが、最も人が集まる東京でもこうした措置が取られた事実は驚きだ。
バス運転手の問題は氷山の一角にすぎない。前回の当コラムでも触れたように、自衛隊は恒常的に定員割れの状態が続いているし、教員の不足も深刻化していると言われる(教員については、いわゆるモンスターペアレンツ対応に伴うストレスや長時間労働など、人手不足以外の要因もありそうだが)。また、民間信用調査機関の帝国データバンクによると、今年度上半期の人手不足を理由とした倒産(資本金1000万円以上)は214件と過去最多を更新し、民間企業も人材難にあえいでいる。
さらに懸念されるのは、少子化を主因にこうした人手不足が中長期的にさらに厳しさを増すのが確実な点だ。毎年の出生数を見ると、今年25歳になる2000年生まれは119万人だったが、2010年には107万人に減り、2020年には84万人になった。少子化はさらに進み、今年は66万人程度に落ち込む見通しだ。25歳の若者の数が、今年に比べ2035年には1割、2045年には3割減り、2050年には半分近くになる計算だ。これまでと同様の経済活動を維持することは、マンパワーの制約により極めて難しくなる。
既に人手不足が顕在化する中、これまで何とか日本社会が回ってきたのは、定年延長による高齢者の活用や女性雇用の増加とともに、過去最高の395万人(6月末日現在)という在留外国人の存在も大きい。このほど外国人問題について日本記者クラブで記者会見した日本総合研究所の石川智久調査部長は、これ以上高齢者を頼りにすることはできないとした上で、「外国人労働者(の受け入れ)に反対する人たちは、人手不足のインパクトが目に入っていないのではないか」と語った。
「やってきたのは人間だった」
石川氏は、現在の日本の外国人政策について、方向性の不在、司令塔の不在、統計の不在という「三つの不在」があると指摘する。外国人をどのように受け入れ、共生していくかの明確なビジョンがなく、中心となって政策を立案・実行するセクションもはっきりせず、関連する統計も不十分、ということだ。この中で早急に対応が必要なのは、方向性を確立することだろう。従来、政府が「移民政策は取らない」としてこの問題から目を背けている一方で、産業界主導のなし崩し的な外国人材の受け入れが続いていたが、もはやそれでは済まされない。政府や国会の場で外国人労働者受け入れのメリット、デメリットを比較考量した真剣な議論が展開され、明確な方向性が示されることを期待する。
議論の結果、これ以上の外国人材の受け入れを制限する可能性もあり、それは一つの選択肢として尊重したい。外国人に頼れないことがはっきりすれば、多くの業種でAIなどを活用した業務の自動化・省力化(バスの自動運転、介護ロボットなど)が急速に進み、人手不足が緩和される可能性もある。逆に言えば、自動化・省力化が進まなければ、経済活動がシュリンクしたり、各種サービスの利便性が低下したりすることを覚悟しなければならない。特に人口減少が進む地方では、外国人労働者により何とか経済活動を維持している業種が少なくないので、インパクトは大きくなるだろう。外国人政策の行方は、日本の経済社会の在り方を大きく左右しそうだ。
最後に一言。移民について論じるとき、スイス人作家の「われわれは労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった」という言葉がしばしば引用される。あたかも機械を導入したり家畜を増やしたりするような意識で外国人労働者を招いたが、やってきたのは独自の言語や文化、習慣を持ち、自尊心もある血の通った人間だった、ということだ。どのような方向性が示されるにせよ、外国人と日本人がお互いを尊重し、違和感なく共生できる社会を目指したいものだ。
■筆者プロフィール:長田浩一
1979年時事通信社入社。チューリヒ、フランクフルト特派員、経済部長などを歴任。現在は文章を寄稿したり、地元自治体の市民大学で講師を務めたりの毎日。趣味はサッカー観戦、60歳で始めたジャズピアノ。中国との縁は深くはないが、初めて足を踏み入れた外国の地は北京空港でした。
関連記事
韓国建設業界で続く外国人労働者雇用の拡大、韓国人の職はなく脅威=韓国ネット「業界の自業自得」
Record Korea
2025/8/4
日本政府がインド人材5万人受け入れへ、民衆は反移民デモ=中国ネット「もう日本に行きたくない」
Record China
2025/10/1
仲介料3万元払って日本へ、技能実習生の「大きな賭け」―中国メディア
Record China
2025/9/25
「家買えば日本に移民できる」は完全な誤解、日本の不動産購入のワナ―台湾メディア
Record China
2025/10/2
中国が新設したKビザに「外国人優遇」懸念噴出、共産党機関紙が反論―香港メディア
Record China
2025/10/3
外国人労働者をいじめた韓国人上司が驚きの理由を告白=韓国ネット「心の傷が早く癒えますように」
Record Korea
2025/7/30