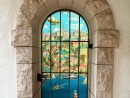中国で「赤ちゃん返り」する人が増加、その背景は?―シンガポールメディア
拡大
シンガポール華字メディア・聯合早報は14日、いまだかつてないプレッシャーにさらされた中国の大人たちの間で「赤ちゃん返り」する人が増えていると報じた。
シンガポール華字メディア・聯合早報は14日、いまだかつてないプレッシャーにさらされた中国の大人たちの間で「赤ちゃん返り」する人が増えていると報じた。
記事は、ライブチャットで配信者がリスナーを「宝貝(バオベイ。赤ちゃん。ベイビー)」と呼ぶケースが増えていること、街中でも老若男女が縫いぐるみのチャームをかばんに付けて歩いていること、ジェリーキャット(英国発の縫いぐるみブランド)のポップアップストアが上海に登場した際には数時間待ちの行列ができたことなどを挙げた上で、「言語表現、服装、消費の選択に至るまで、これらの兆候は一つの明確な傾向を示している。それは、ますます多くの中国の大人が『赤ちゃん』に戻っているということだ」と論じた。
そして、こうした現象は世界的に珍しくなく、1950年代には欧米ですでに「キッド」と「アダルト」を組み合わせた「キダルト」という概念が生まれていたことを紹介。「子ども向け番組を好んで視聴する大人を指す言葉で、テレビ局は大人の視聴者を引き付けるために、アニメの放送時間を仕事帰りの時間帯に設定することさえあった」とした。また、エコノミスト誌が2023年に再び「大人の子ども化」を取り上げ、英国やスペインなどでは多くの大人が子ども向け施設を訪れていることも例として挙げた。
その上で、中国における「子ども化」について「現代の中国の経済・社会環境と深く結びついている」と言及。「急速な経済成長と資産拡大を経験してきた大人たちは現在、失業やリストラ、資産価値の縮小といった現実に直面し、前例のないプレッシャーや物悲しさを感じざるを得ない状況にある。そうした中で『赤ちゃん』に戻ることは、かつての好景気時代を懐かしむと同時に、感情的な息抜きにもなっている」との見方を示した。
また、「大人だけでなく中国の若者層も十分な成長の機会に恵まれていない」とし、先日、中国の複数の大学で「保護者会」が開かれたというニュースが大きな議論になったことを紹介。「大学は本来、若者が自立に向かうステージであるはずなのに、保護者が大学運営に介入することはそれを妨げ、社会に『ビッグベビー(巨大な赤ちゃん。見た目は大人だが精神的には赤ちゃん)』を生み出してしまうのではないか」というのが否定派の意見だとした。
記事によると、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の閻雲翔(イエン・ユンシアン)教授は今年5月、「拡張型青春」という概念を提唱し、中国のZ世代の思春期が前後で延長されていると指摘した。閻氏によると、デジタル技術やSNSで子どもが早熟化する一方、若者が大人になることを意識的に遅らせたり避けたりする傾向があるという。その背景には、生活コストの上昇や不安定な就業市場といった経済的要因だけでなく、現代の若者が社会的期待よりも個人的な満足感を優先する傾向があることも関係していると分析している。
「中国知的財産(IP)玩具産業レポート」によると、20~24年の中国のIP派生商品市場の年間平均成長率は15%を超え今年の市場規模は2025億元(約4兆2000億円)を突破すると予想されている。また、EC大手の京東(JD.com)が今年の児童節(子どもの日)に行った調査では、大人の56.8%が自分用に玩具を購入し、51.1%が「自分のために児童節を祝う」と回答したという。
記事は、「たとえ短時間だけ『赤ちゃん』に戻り、ぬいぐるみで心の癒しを得たとしても、結局は厳しい現実世界に戻らざるを得ない。失業リスクは依然として存在し、不動産価格の下落による損失回復には時間がかかる。社会保険の追納や退職年齢の延長といった現実的な課題が次々と目の前に立ちはだかり、避けては通れない問題となっている」と論じた。(翻訳・編集/北田)
関連記事
欧州の自動車産業、独専門家「中国がすべての切り札を握っている」―台湾メディア
Record China
2025/9/16
搭乗拒否で日本に行けず、台湾人女性が訴えも逆に批判殺到
Record China
2025/9/15
トランプ氏が長年の同盟国を怒らせる、日韓で貿易協定への不満高まる―シンガポールメディア
Record China
2025/9/15
台湾人だらけなのになぜ済州島ではなく沖縄に行くのか、台湾ネットで反響―台湾メディア
Record China
2025/9/15
米国で拘束された韓国人労働者の帰国が外交の敏感期を誘爆―シンガポールメディア
Record Korea
2025/9/15
火鍋チェーンの放尿事件、関与した未成年者の両親に4400万円相当の賠償命じる判決―中国
Record China
2025/9/15