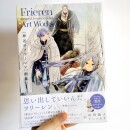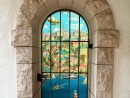「鬼滅の刃」に見る日本近代性の隠喩―台湾メディア
拡大
30日、台湾メディアのThe News Lensは「『鬼滅の刃』に見る日本近代性の隠喩」と題した記事を掲載した。写真は鬼滅の刃。
2025年8月30日、台湾メディアのThe News Lensは「『鬼滅の刃』に見る日本近代性の隠喩」と題した記事を掲載した。
記事はまず、「『鬼滅の刃』物語は、鬼と人の永遠の戦いを描いている。人間の世界にもともと鬼はいなかったが、病に支配されないことを望んだ人間が、薬の歪んだ作用によって、活動時間を制限されながらも『無限』に命を延ばすことができる鬼へと変貌したのだ。また新たな鬼が無限に生み出され続けたことで、鬼と人との戦いは避けられないの永遠のもつれとなり、劇場版『鬼滅の刃』無限城編にて、ついにその最終決戦が幕開けとなった」とし、「『鬼滅の刃』からは、近代以降の日本社会を象徴するいくつかの要素が読み取れる」と言及した。
その上で、「無限城編においては上弦の参・猗窩座(あかざ)との戦いが象徴的に描かれている。猗窩座は武器を使わずに素手で戦う格闘術を極めており、さらに肉体への執着を捨て去ることで戦闘能力の頂点に達していた。最終的には竈門炭治郎(かまどたんじろう)が、父の舞から『透き通る世界』を会得し、自らの闘気を極力消すことで、猗窩座の首を斬ることに成功する。しかし、首を失った肉体ですら猗窩座はなお戦い続け、自らの強さを証明しようと執念を燃やした」と説明した。
続けて、「ここで浮かび上がるのは、猗窩座の闘志が第二次世界大戦における日本の精神力を体現しているという点である。例えば、神風特攻隊や肉体の力だけで最後まで勝利を目指そうとした精神力は、真珠湾攻撃のように自らの強さを証明する試みをもたらし、そして広島・長崎への原爆投下という結末を招いた。猗窩座は首を失ってもなお闘志だけで戦おうとしたが、大切な人の存在に気づき、失ったものが首ではなく『心』であったことを悟るのである」と述べた。
また、「無限城編のもう一つの焦点は、上弦の弐・童磨(どうま)と上弦の陸・獪岳(かいがく)にも示されている。童磨は両親が教祖である宗教団体で祭り上げられていた。彼は形式ばかりの宗教や人間が無意識に他者に従ったり利用されやすい性質を見抜き、自身を他人の崇拝や依存を吸い寄せる『食人花』のような存在に変貌させる。この観点から見ると、蟲柱・胡蝶(こちょう)しのぶとの対決は、まさに食人花と毒虫の戦いのようである」とした。
一方、「獪岳はもともと孤児で、鳴柱に面倒を見てもらっていたが、『雷の呼吸 壱ノ型』を習得できない挫折を克服できず、弟弟子の我妻善逸(あがつまぜんいつ)を拒絶するようになった。最終的に自分の理想を追い求めて迷走した獪岳は、善逸が『壱ノ型』から独自に『漆ノ型』を創出し、自分を斬ったことに驚愕することになる。作中の鬼たちは生前それぞれ家族との絆を持っていたが、特定の執念に基づく自分を追求するあまり、その力や命を無限に拡大しようと鬼になってしまう。ここでは、日本近代史における家族(大名、貴族、財閥)の力が国家の原動力となりながらも、軍国主義によってその絆や価値が犠牲にされていった過程が透けて見える」と論じた。
そして、「最後に特筆すべきは、『鬼滅の刃』で繰り返し登場する生物学的な概念である。作中の鬼は血を与えられることで増殖し、逆に特定の薬や抗原で弱体化させられることもある。この描写は、従来の妖怪や鬼のイメージとは異なり、近代化が進む中で道徳心から逸脱し、迷走した日本社会の象徴とも言える。そのため鬼殺隊は、珠世(たまよ)が開発した薬を使って鬼の力を弱体化させた上、強い意志と剣技によって無惨を討った。『鬼滅の刃』では鬼と人との戦いを通して、死や権力といった現実の重圧に立ち向かう姿が描かれる。すなわちこれは、近代以降に薄れつつある日本社会の倫理観や価値観、心の在り方を問い直しているのである」と結んだ。(翻訳・編集/岩田)
関連記事
「鬼滅の刃」無限城編、童話を超えた新世代の「国民的アニメ」に―香港メディア
Record China
2025/9/5
「鬼滅の刃」無限城編、猗窩座の悲劇が映す大正ロマンの影とは―台湾メディア
Record China
2025/9/3
台湾で「鬼滅の刃」無限城編の興収が無限列車編を超える、ネット「煉獄さんは負けてない」―台湾メディア
Record China
2025/9/1
「鬼滅の刃」の興味深い設定、炭治郎はもともと主人公ではなかった―台湾メディア
Record China
2025/8/30
中国アニメは「鬼滅の刃」の成功にどこまで迫れるのか―中国メディア
Record China
2025/8/30
「鬼滅の刃」鑑賞後にポップコーンめぐり口論―台湾
Record China
2025/8/28