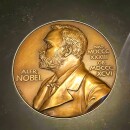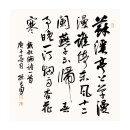「火垂るの墓」の清太とおばさんどっちが悪い論争が表すもの―中国メディア
拡大
中国のニュースサイト・観察者網に24日、「戦争の悲劇を少年のせいにすることが日本で主流の見解になっている」との文章が掲載された。資料写真。
中国のニュースサイト・観察者網に24日、「戦争の悲劇を少年のせいにすることが、日本で主流的な見解になっている」との文章が掲載された。
文章は、終戦記念日にあたる15日に金曜ロードショーで放送されたスタジオジブリの「火垂るの墓」に言及。「日本ではしばしば共通の記憶の象徴として扱われてきた作品である。終戦記念日の前後に放送されることが多く、日本人にとって戦争を振り返り、平和を記念する文化的シンボルとなっている。同作を『国民的な戦後の記憶のトリガーである』とする日本文化研究も存在する」と説明した。
一方で、「そうした効力は次第に薄れつつある」とし、「敗戦から80年を迎える節目の放送で、多くの視聴者は清太一家の悲惨な運命を通じて、戦争を反省するのではなく、悲劇の責任を1人の少年のわがままのせいにしようとしており、その風潮は不安を抱かせるものだ」と指摘。同作のストーリーと、「清太と西宮のおばさんのどっちが悪いか論争」を紹介した。
文章は、「かつて同作に対する感想の中心は『戦争は本当に恐ろしい』『清太一家は本当にかわいそう』『おばさんは冷血』といったものだったが、現在では西宮のおばさんに共感する見解が広まりつつある。簡単に言えば、『清太はダメ人間であり、戦火の中で家族を支えたおばさんこそが善人だ』というものだ」とした。
そして、「清太をダメ人間と批判する人たちには2つの理由がある」とし、「1つは清太が恩知らずだという点。清太らがおばさんの家に来た時に食糧を持参したことや、おばさんが食事で2人に差別的な扱いをしたことは事実ではあるが、それでも面倒を見てもらっているのだからふてくされたりせず、感謝の態度を示すべきというもの。もう1つは清太が自己中心的すぎるというもので、『おばさんの家に身を寄せていた時に清太は働きもせず、国のために尽くさなかった。だから食糧を減らされるのは当然。それにもかかわらず、清太は妹(節子)とともにおばさんの元を離れたことで、結果として妹を死なせることになった』というものだ」と説明した。
文章は、この問題への考え方の違いは世代によっても現れているとし、若年層ではおばさんに反発し、清太に同情する意見が多い一方、現役世代や中年層では働きもしない清太が悪いと考える人が多く、さらに上の高齢層では「14歳ではそんなもの」と清太に同情的な意見が多くなっていると紹介。そして、「清太を批判する人々の認識は、従来『清太は戦争の犠牲者』と共感を寄せてきた年長世代の感覚とは対照的であり、結果として『清太と西宮おばさんのどちらが正しいか』をめぐる議論が噴出している」とした。
その上で、「同作がこうした家庭内の倫理ドラマとして矮小化され、清太がわがままな少年と解釈されてしまうと、同作が訴える歴史的警鐘は無力化され、社会の感情も『戦争の残酷さを反省する』方向から『個人の責任を厳しく追及する』方向へと色を変えてしまう」と懸念を示し、「これは日本社会のより深い変化を映し出している。それは『弱いことは罪である』という冷酷な論理で、『他人を助ける余力はないのだからおばさんは正しい』という言説の背後には、弱者を恐れる感情がある」と分析した。
そして、「近年の日本のニュースでは、障害者、高齢者、低所得者、外国人労働者を社会の負担や問題として露骨に扱う言論が増えていることを実感できる」と指摘。神奈川県相模原市の障害者施設を襲撃し入所者ら45人を殺傷した植松聖死刑囚に一部の極端なネットユーザーらが共感を示していること、イェール大学アシスタント・プロフェッサー成田悠輔氏が「高齢者の集団自決」を口にして物議を醸したこと、生活保護受給者への批判が厳しさを増していること、外国人を敵視することが増え「日本人ファースト」を掲げた参政党が先の参院選で躍進したことなどを挙げた。
文章は、「このように問題を弱者に帰する考え方は、失われた30年の後の日本の長期的な経済停滞の必然的な結果である」と言及。「バブル経済の崩壊以降、日本の伝統的な集団主義の倫理観や終身雇用制度は揺らぎ、小泉純一郎政権は財政赤字や長期停滞、社会的不満に対応するため、2000年代初頭に一連の自由主義的改革を推進した。構造改革を名目に市場化を推進し、公共支出を削減する一方、自己努力を強調し始め、こうした『自己責任論』が広まるにつれて、貧困や失業、不安定雇用は次第に個人の努力不足の結果として説明されるようになり、社会的困難も世論の中で個人へ転嫁されるようになっていったのである。しかし20年以上が経過し、現実のデータは明確に示している。たとえ大多数の人々が全力を尽くしても、半数以上の家庭は生活に窮しているとの実感があるのだ」と論じた。
そして、「社会学研究によると、経済的困窮や階層の固定化、資源分配の逼迫といった環境では、集団は不満や不安を社会で最も抵抗力のない層に投影しやすくなり、弱者差別の心理が広く形成されるそうだ。弱者を攻撃する心理と、清太を責める言説は、このような時代背景の中で恐ろしい一致を示している。巨大な不確実性と圧力の中で、『清太は自業自得だ』と自分に言い聞かせることで、『自分がきちんと努力すればこんな状況に陥ることはない』と安心感を得るのだ。しかし、同作において清太も西宮のおばさんも被害者であったように、経済の構造的問題や社会的不平等は、個人の行動や努力によって消えるものではない」と論じた。
その上で、「火垂るの墓」の監督を務めた高畑勲氏がかつて「当時は非常に抑圧的な、社会生活の中でも最低最悪の『全体主義』がはびこっていた時代。そんな時代においては、あの西宮のおばさんの言うことは何でもなかった。清太の失敗はそんな『全体主義』の時代に恐ろしく『反時代的』な行為に走ったこと。現代の若者や私たち大人が心情的に清太を理解しやすいのは、時代が逆転し、価値観が反転したから。でも、再び時代が逆転したとしたら、あの西宮のおばさん(のこと)以上に清太を糾弾することにならないか。僕はそれが恐ろしい」と語っていたことを伝えた。(翻訳・編集/北田)
関連記事
高畑勲監督の「火垂るの墓」、中国人はどう評価しているのか
Record China
2018/4/13
一生のうちに見ておくべき日本のアニメ5作品、中国ネットは賛否=「初めて見た時には震えた」「あれが入ってないなんて正気?」
Record China
2016/1/10
「見る前にはティッシュを用意」「子どもが見るには適さない」、日本の有名映画に反響続々!―中国ネット
Record China
2014/5/21
「となりのトトロ」が成功したのはなぜ?ー中国メディア
Record China
2018/12/16
「ジブリアート展」が上海で、世界初公開の展示も―中国メディア
Record China
2024/4/2
「もののけ姫」に中国人から感謝の声=「前向きに生きることの大切さ教えてくれる」―中国メディア
Record China
2025/5/9