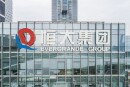中国で進む次世代ハブ空港の拡張競争、広州・南通・大連が新ハブ戦略
拡大
中国の航空ネットワークは大転換を迎えている。写真は広州白雲空港。
中国の航空ネットワークは大転換を迎えている。広州白雲空港の第3ターミナル建設、南通に誕生する「上海第三空港」、そして大連・金州湾で進む世界最大級の人工島空港。いずれも日本企業の出張や物流ルートに直結するプロジェクトだ。
広州白雲空港、「花冠」ターミナルで世界最大
広州白雲国際空港の第3ターミナル(T3)が8月に検収を通過し、年内の投入運用が確実視される段階に入った。新ターミナルは「花冠」をモチーフにしたデザインで、8枚の花弁が広がるような外観を持つ。
白雲空港全体の処理能力は完成時点で年旅客1億2000万人、貨物と郵便380万トン、将来的には1億4000万人、600万トンへと拡張される見込みだ。華南経済圏における国際ゲートウェイとしての存在感は一層強まり、日本からの出張者にとっても利用頻度の高いハブ空港となることが見込まれる。
上海第3空港がいよいよ現実に
一方、長江デルタでは、南通新空港の建設が現実のステージへと移り、「上海第3空港」計画が一気に前進した。上海空港(51%)と南通城建(49%)は15日、共同で「滬蘇南通新機場建設投資有限公司」を設立した。登録資本金は10億元(約200億円)。
新空港は浦東・虹橋と並び、長江デルタの三極構造を形成することを目指しており、将来的には国際線の分散運航を担う可能性が高い。南通は近年、製造・研究開発拠点として日系企業の進出も増えており、日本からの直行便就航に向けた期待感は強まる一方だ。
大連・金州湾人工島空港、北東アジアの新たなハブへ
さらに北東部では、大連・金州湾に世界最大級の人工島空港が建設中だ。6月に地盤改良工事が第2ステージに入り、プロジェクトは本格的な基盤整備段階へと進んだ。
完成予定は2035年とまだ先の話だが、最終計画では滑走路4本と90万平方メートルの旅客ターミナルを備える。初期段階で年4300万人、将来的には8000万人を超える処理能力を誇る巨大空港へと成長する見通しだ。北東アジアの国際拠点としての役割は明らかであり、韓国、日本、ロシア極東を結ぶ戦略的ハブとしての位置づけが固まりつつある。
高原空港が拡張、西安では空港博物館
内陸部では高原地帯の玄関口が大幅に拡張されている。青海省の西寧曹家堡空港が新ターミナル(T3)を7日に稼働したからで、2030年には旅客2100万人、貨物輸送12万トン規模を目指す。日本でいえば信州のアルプス地帯に国際空港が登場するのに相当するだろうか。
さらに陝西省の西安咸陽国際空港第5ターミナルビル(T5)の運用が2月20日に始まり、同省で発掘された文化財を展示する「空港博物館」も登場した。年間8000万人規模を処理できる内陸最大のハブ空港へ成長する見通しで、これまで沿海部に偏ってきた空のネットワークが広く西域にも広がりつつある。
国内インフラを超えた空港ビジョン
総じて言えるのは、中国の空港整備はもはや単なる交通インフラにとどまらなくなっていることだ。「国際化」「分散化」を体現し、広州や上海の巨大ハブを補完しつつ、地方都市も国際舞台に登場させようとしている。
日本企業にとっては、出張ルートの再設計や物流ネットワークの組み替えを迫られると同時に、新たな市場にアクセスできるチャンスともなる。空港拡張のニュースは単なる建設工事の話題にとどまらず、「次のビジネス戦略地図」を描くための羅針盤でもあるのだ。(提供/邦人NAVI-WeChat公式アカウント・編集/耕雲)

関連記事
なぜ妻と息子が日本旅行を選ぶのか理解した―中国人男性
Record China
2025/8/20
空港で回収された不合格のモバイルバッテリー、ネットで売られる―中国
Record China
2025/8/18
上海の空港の搭乗ゲート付近が「まるで図書館の自習室」―中国メディア
Record China
2025/8/17
日本のバス停で見た「面白い光景」とは? 中国ネット「文明社会のあるべき姿」「中国なら…」
Record China
2025/8/18
上海の空港で「二重セキュリティーチェック」を撤廃、24時間運用と睡眠カプセルに続くアップデート
邦人Navi
2025/8/16
韓国仁川空港に行くはずが金浦空港に到着、マレーシアLCCがハプニング=韓国ネット「あきれる」
Record Korea
2025/8/16