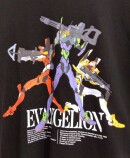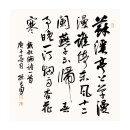「性蕭条」と少子化、日米中に広がる出生率低下と中国の対応
拡大
日本、米国、中国の出生率はいずれも人口維持水準を下回る。背景には晩婚化や経済的不安などの共通要因に加え、各国固有の事情がある。写真は上海。
日本、米国、中国の出生率はいずれも人口維持水準を下回る。背景には晩婚化や経済的不安などの共通要因に加え、各国固有の事情がある。中国は育児手当や結婚奨励策を導入するが、「性蕭条」が壁として立ちはだかる。
出生率低下の現状
日本の合計特殊出生率は2024年に1.15となり、出生数は70万人を下回った。中国は22年に1.09を記録し、24~25年は1.0前後に低下する見通しだ。米国は1.6~1.7の範囲で推移し、日中と比べて高い水準にあるが、やはり人口維持に必要とされる約2.07には届かない。出生率の低下は労働力人口の縮小、社会保障の負担増、需要構造の変化を通じて、企業活動と家計双方に長期的影響を及ぼす。
共通する背景と国ごとの事情
少子化に突入した国々では、晩婚化・晩産化、未婚率の上昇、女性の高学歴化と就業機会の拡大、子育て・教育コストの上昇といった問題が顕著になっている。経済的不確実性が強まる局面では、出産を先送りしたり、断念したりするケースが増えやすい。
日本:
出産年齢層の人口減少、長時間労働、支援制度の不足が影響する。
中国:
15年まで続けられてきた一人っ子政策の影響、都市部の高い住居・教育費が障壁となる。
米国:
経済格差の拡大により若年層の雇用・所得が不安定化し、結婚・出産の時期が遅れる。
中国の「性蕭条」と少子化対策
こうした中、昨今中国で注目を浴びているキーワードに「性蕭条」がある。人々が性的関心や活動が減少することを指す概念で、日本語では「性不況」と訳されることが多い。性生活頻度の減少、アセクシャル婚の増加、若者の恋愛・結婚への意欲低下といった現象が挙げられる。背景には将来の不安、経済・精神的負担、消費意欲の低下、夫婦間コミュニケーション不足がある。
そこで中国では25年に全国で3歳未満1人当たり年間3600元(約7万2000円)の育児手当を導入し、約2000万世帯を対象とする政策が講じられる運びとなった。地方における試行では、出生数が増加した事例も確認されるという。一方で、支給額の規模や家族政策支出が国際比較で見て低い水準にとどまっていることから、現時点ではその効果は限定的なものにとどまるとの指摘もある。
婚姻数減少と今後の展望
少子化問題に直結する「少婚化」も顕著だ。中国の24年の婚姻登録数は前年比20.5%減の610万6000組で、過去最低を記録した。25年第2四半期(4~6月)は354万組とやや回復したものの、非婚出産の割合が低い中国では婚姻数の減少が出生数の減少に直結する。結婚費用の軽減や祝い金支給といった奨励策の効果は限定的で、経済、雇用、住居、教育といった生活基盤の改善を含む総合的アプローチが求められる。(提供/邦人NAVI-WeChat公式アカウント・編集/耕雲)

関連記事
韓国の65歳以上人口が初めて1000万人突破、少子化進むも外国人が増え総人口は増加
Record Korea
2025/7/30
日本の外国人問題はどれほど深刻なのか―中国メディア
Record China
2025/7/19
韓国軍の規模が6年で20%減少、原因に少子化―中国メディア
Record Korea
2025/8/11
少子化対策に必要なのは愛と給付と結婚休暇?中国で広がる長期婚休と日本の現実
邦人Navi
2025/6/15
マスク氏の日本に関する大胆予言が現実に?最新データに震える―台湾メディア
Record China
2025/6/6
「3頭のクマのオブジェが少子化を助長」ソウル植物園が苦情受け撤去へ=韓国ネット「何の関係が?」
Record Korea
2025/5/8