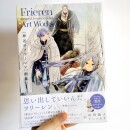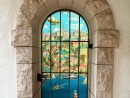<サッカー>「日本の子は誰も弱音を吐かなかった」=元中国代表選手が「日本に学ぶ」と決めた理由
拡大
中国で「日本式育成」を掲げてユースクラブを立ち上げたサッカー元中国代表FWの楊旭氏が日本と中国のユース育成の違いについて語った。
中国で「日本式育成」を掲げてユースクラブを立ち上げたサッカー元中国代表FWの楊旭(ヤン・シュー)氏が日本と中国のユース育成の違いについて語った。中国のスポーツメディア・新浪体育が25日に報じた。
2023年4月11日、当時35歳のプロ選手だった楊氏は自身のライブ配信で現役引退を発表した。上海申花との契約は残っており、まだまだプレーできる状態だった。それでも引退を決めたのは新たな目標ができ、それをすぐにでも始めたかったからだという。楊氏が新たに見つけた道は「ユース育成」で、明確な方針として「日本に学ぶ」ことがあった。引退から3カ月後、上海市長寧区で楊氏のユースクラブが発足した。クラブ名は「朝日」。自身の名前である「旭」と同じく「昇る太陽」という意味があることのほかに、「日本に学ぶ」という方針を象徴する名前でもあるという。
楊氏が日本式のユース育成を学び、それを手本として導入しようと決めたのは、彼自身が息子たちにサッカーを学ばせた経験によるものだった。2022~22年に楊氏は2人の息子を日本人コーチの下で学ばせた。22年末には、楊氏自身が2人を連れて東京に3カ月間滞在してトレーニングを行い、この経験がユース育成を日本に学ぶという決意を固めるきっかけになったそうだ。
子どもに海外でサッカーを学ばせる中国の親の間では、「欧州派」と「日本派」に分かれている。スペインに渡る家族は200~300組ほどある一方で、日本に行く家族は数十組程度。そうした中で楊氏が日本を選び、さらに日本式の育成法を中国国内に導入しようとしているのは、それがアジア人により適したやり方だと確信しているからだ。楊氏は「私はこの目で見てきた。日本のユース育成は非常に基礎がしっかりしていて、システムとしても整っている。子どもたちは6~14歳にしっかりとした基礎を築いている。それを持って欧州でさらに進化すれば、選手としての上限も高くなる」と語った。
また、「何を学ぶかを決めるには、まず自分たちに何が足りないかを知らなければならない。日本はアジアと欧州のサッカー文化の違いや人種の違いにまで踏み込んで、それに合わせた指導方法と成果を導き出している。日本が欧州のレベルに追い付いてきたのは、どこか一つの強豪国を模倣したのではなく、相手の長所と短所を分析し、何が自分たちに適しているかを見極めた上で、それを研究し、具体的な方法として取り入れてきたからだ」と論じた。
日本式のユース育成を学ぶにあたり、楊氏が取った方法は、優秀な日本人コーチを招いて特別指導を行わせること。そして日本のユースクラブと提携し、日本式に近いトレーニング体系と環境を構築することだった。楊氏は「私の上海のクラブでは、日本人の子どもたちも一緒にトレーニングに参加している。彼らはまるで“小さなアシスタントコーチ”のような存在。日本の子どもたちは練習中の集中力が高く、効率もよく、強度もある。そうした姿が中国の子どもたちに良い習慣を身につけさせてくれる」と語った。
楊氏によると、現在の中国のユース育成は、自身の子どもの頃とやっている内容自体はさほど変わっていないうえ、大事なものを失ってしまっているという。「今の中国のユース育成は、科学的トレーニングばかりを重視して、根性(気持ちの強さ)を捨ててしまった。雨が降ったら練習中止、雪が降ったらやらない、暑ければやらない。子どもたちはとてもか弱くなってしまった。親も過保護で、何でも手を出すから、子どもたちは自主性を失っている」と楊氏は嘆いた。
そして、「日本のサッカーは週3回の練習だが、それ以外の日は自主的に別のクラスを取って練習する子も多い。しかも彼らの練習と試合の強度は非常に高い」とし、「私の次男がある試合に参加した時は、朝から夕方まで試合をして、そのあとにコーチからインターバル走の追加を命じられ、35分間走らされた。うちの子は泣きながら最後まで走ったが、日本の子どもたちは平然としていて、誰も弱音を吐かなかった。彼らは、そういう強度に慣れている」とも語った。
楊氏のように、引退後にユース育成に関わるケースは少なくないものの、その多くが長く続かないという。楊氏はその理由に「待遇の低さ」と「労力」を挙げ、「ユース育成の報酬はプロチームの指導とは比べ物にならない。それに、ユース指導のほうが頭を使う。プロチームなら出来上がった選手を組み合わせるだけでいいが、ユースは人を育てる仕事、チームを育てる仕事で、これには時間がかかる。大人と同じように教えても子どもには伝わらない。わかりやすくかみ砕いて教える工夫が必要になる」と述べた。
その上で、「日本には、引退した元プロ選手が長期的にユース世代を指導している例が多くある。その根本的な理由は、やはりサッカー愛だ。彼らはサッカーが本当に好きで、自分の持っているものを子どもたちに伝えるのが楽しい。だからこそ、多くのものを犠牲にしても続けていける」と指摘。「私の子どもが日本で所属していたチームにはコーチが11人いたが、そのうち6人は報酬なしのボランティアだった。昼間は別の仕事をしていて、夜に子どもたちを指導していた。それができるのは、心からサッカーが好きだからだ」とした。
楊氏はさらに、川崎フロンターレのコーチに聞いた「子どもが小さいうちは足し算をする時期で、いろんな技術を練習させる。12歳を過ぎてから引き算を始める」との言葉を紹介。「つまり、12歳までにしっかりと技術の土台を築き、その上で『パスが上手い』『スピードがある』『頭がいい』選手を選び出し、戦術に適応させるということ」と説明した。
一方、中国については「子どもが小さいうちから引き算をしてしまう。結果を出すために、ミスを恐れて子どもにドリブルをさせず、ロングボールを蹴らせる。こうした単純で強引なプレーはユース年代では一時的に成果を出せる。でも子どもたちが成長して、自分自身で引き算しようとしたときには、すでに引くものが残っていないことに気づく」と言及。「中国では上から下まで功利的で勝利が最優先になり、子どもがサッカーを通して成長できるかどうかは二の次になっている」と指摘した。
楊氏は「ここ十数年、中国サッカーはあまりにも多くの遠回りをしてきた。成果を急ぎすぎて、近道だと思ったものは実は偽の近道だった。本当に必要なのは、これからの10年で基礎を固め、一つの世代を育て上げること。その過程では、たとえベトナムに負けようが、タイに負けようが、ミャンマーやラオスに負けようが、決してブレてはいけない。10年後に結果が出ることを信じて続ける覚悟と信念が必要だ」と語った。(翻訳・編集/北田)
関連記事
サッカー元中国代表FW「日本に来て認識が覆された」―中国メディア
Record China
2024/12/23
「日本の子がうらやましい」=来日した中国のサッカー少年が涙
Record China
2023/8/10
<サッカー>背後から猛突進、相手を蹴り骨折させる=中国ネット「これはもう犯罪」
Record China
2025/5/29
日本の高校サッカー決勝を生観戦、元中国代表FW「日本はまた1年進歩し、中国はまた1年足踏み」
Record China
2024/1/11
<サッカー>日本戦で惨敗、中国の識者はどう見た?=「絶句だよ、絶句!」「これが日本との真の差」
Record China
2024/9/6
<サッカー>日本と中国の子どもが練習、視察した中国協会会長も「明らかな差」を実感―中国メディア
Record China
2025/1/10