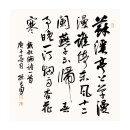日本にどんどん似る中国の恋愛・結婚事情=中国ネット「日本より悲惨」「本当に日本に似るなら…」
拡大
中国のSNS・微博(ウェイボー)に14日、日本と中国は特に男女の恋愛・結婚という面で似通っているとの文章が投稿され、反響を呼んだ。
中国のSNS・微博(ウェイボー)に14日、日本と中国は特に男女の恋愛・結婚という面で似通っているとの文章が投稿され、反響を呼んだ。
微博で250万超のフォロワーを持つブロガーは「私が『中国は将来的に日本のようになる』と言うたびに、なぜか分からないが過剰反応する人がいる」とし、「だが客観的な事実はそこにある。避けたいのなら何らかの変化を起こさなければならない」と主張した。
同ブロガーは具体的に、「バブル経済の絶頂期、日本社会では『恋愛資本主義』という価値観が広まった。男性の価値はその消費能力によって決まるというもので、恋愛では『高価な贈り物=愛』という暗黙のルールが存在していた。企業も男は女のために金を使うべきと盛んに宣伝し、結果、男性たちは大きな経済的負担を強いられた。実は中国でも、この段階はすでにほぼ通り過ぎたと言える。表現のされ方こそ違えど、中国の男性もまた結婚のために金をつぎ込むというほぼ同じ過程をたどった」と述べた。
次に、「日本はその後、消費の合理化へと進んだ。男性の消費はパートナーのためから自分への投資へと移行し、健康維持やデジタル機器、趣味関連の消費が急増した。健康サプリの売上が大幅に伸びていることからも、彼らの関心が自分の生活の質へと向かっていることがうかがえる」と指摘。「この点も、中国で徐々に変化しつつある」とし、中国でキーボード市場やゲームコントローラー市場が伸びていること、「黒神話:悟空」といったゲームに多くの男性が課金していることを挙げ、「いずれも男性の消費がパートナーのためから自分のためへとシフトしていることを示している」と評した。
さらに、「結婚の崩壊」について、「日本では女性は結婚してキャリアを手放したくないという思いがあり、しかも(家庭に入ると)家事の90%を負担しなければならないという現実から、結婚や恋愛に対する魅力が低下している。男性は家族を養う負担が大きすぎる上、離婚時には(女性に収入がなければ)高額の扶養費(財産分与)を払わねばならず、結婚への恐怖感を強めている」と分析。「中国では、女性の間で結婚は抑圧であり、罪悪であるという意識が広がっている。男性側としても、(将来的に)子どもも、財産も、尊厳も、すべて失う可能性があり、『結婚は何も得るものがない』と感じられるようになっている。そうした感情が広がり、結婚や恋愛への積極性は史上最低レベルになっている」とした。
このほか、「社会の階層化が深刻になっている」とし、「日本では経済力が結婚・恋愛における核心的なハードルになっている。年収1000万円を超える女性の未婚率は30%未満である一方、低所得の男性たちは完全に婚姻市場から排除されており、結婚と恋愛における階級の固定化が進んでいる。中国でも、社会の最下層にいる男性たちの大多数はすでに婚姻市場から排除されており、低年収ではお見合いすらしてもらえないのが現実だ」と指摘した。
その上で、「これらの(日中の)状況は細部こそ異なるものの、大まかには似通っている。日本ではこうした状況を背景に、援助交際やパパ活が生まれた。性への需要がある一方、所得格差が広がり拝金主義がまん延した結果だ。そして中国でも、今やそうした土台は整いつつある」と述べている。
中国のネットユーザーからは「(中国は)日本よりも悲惨に見える」「日本のまねができるならまだいい。もっとひどくなると思う」「日本は(国として)豊かになったことがあるが、われわれの方はほとんどの地域がまだ豊かにもなっていない」「(中国は)大都市であればあるほど、実は女性の方が結婚相手を探しにくいんだよね」「男性は多少妥協して相手を選ぶけど、女性は絶対に妥協しないから」「(日本の)援助交際はずっと前からあったけどな」「本当に日本に似るのなら、男女の他に男男や女女もにぎやかになる」「社会秩序の再構築にはしばしば戦争が必要になる」「日本のバブル時代になったらいいのにな」といったコメントが寄せられている。(翻訳・編集/北田)
関連記事
日本の女子高生の「裏の顔」を中国人の男子生徒が暴露=「一番腹が立つのは…」
Record China
2024/12/4
中国の中学生カップルの大胆なキス写真が日本のネット上で話題に!?中国ネット「ほんの一部の生徒だよ」「今では小学生もやってる」
Record China
2016/8/19
「日本人が夜中にイチゴを持ってきた」、中国人留学生の投稿が大反響=「かなり大胆」「気になるのは…」
Record China
2024/3/13
「日本の女子高生のスカートの秘密」に中国人も大興奮!?=「そうだったのか!」「日本へ旅行に行った時に…」
Record China
2016/6/10
中国人の日本旅行にある特徴!?「私、今まさにそう」「10回行ったけど8回は…」
Record China
2025/6/19
日本の高校生カップルの生活に中国人衝撃=「本当?」「われわれの運命は…」
Record China
2025/2/15