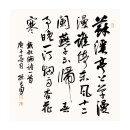米国による中国封じ込め、科学技術「自力更生」に時間かかるが突破は可能―香港誌
拡大
米国は科学技術分野での「中国封じ込め」を続けている。香港誌の亜洲週刊はこのほど、「時間はかかるが突破は可能」と論じる記事を掲載した。写真は中国製の電気自動車。
米国は2020年以降、国家安全保障の名の下に、中国が自国の最先端技術を利用することに対する制限を強化してきた。中国企業や中国の産業構築が大きな影響を受けているのは事実だが、中国側は米国による「中国封じ込め」を突破しようと努力を続けている。香港誌の亜洲週刊はこのほど、「時間はかかるが突破は可能」と論じる記事を掲載した。以下は、同記事の主要部分を再構成したものだ。
中国企業が選んだ手段としてはまず、例えば人工知能関連の機器を、第三国を通じて中国に持ち込むことがあった。しかし、このような方法は米国の圧力により困難が増している。そこで中国企業は、データを国外にいったん移すことで、東南アジアや中東などの地域で米国のAIチップを利用する方法へと転換している。
例えば「ウォール・ストリート・ジャーナル」によれば、3月初めに中国人技術者4人がマレーシアに行った。技術者4人は、人工知能(AI)モデルの訓練に使用するための80テラバイト(TB)のスプレッドシート、画像、動画クリップを保存したハードディスクを持参していた。一方で、技術者の雇い主は、マレーシアにあるデータセンターで、米国の半導体企業であるNVIDIA製の高性能AIチップを搭載したサーバー約300台を借りており、技術者は持参したデータをサーバーに入力してAIモデルを訓練した後に、成果を中国に持ち帰る計画という。
米国は中国に対して輸出規制、投資制限、技術供給の遮断などあらゆる措置を重層的に発動する「科学技術戦争」を仕掛けた。しかし効果は限定的と見られる。米国政府は中国企業の抜け道を見抜けずに頭を悩ませており、バイデン政権時のレモンド商務長官は退任前に「米国の科学技術の封鎖はほとんど徒労に終わった」と嘆いた。
米国にとっては、中国企業による「抜け穴探し」よりも、本質的に深刻な事態が進行している。「自力更生」を迫られた中国が、挙国体制で巨額の資源を投入して研究開発を進め、すでに多くの成果を上げつつあることだ。習近平国家主席は、「鍵となる技術は求めても得られず、買おうとしても買えず、交渉しても得られない。それらを自らの手で掌握して初めて国家の経済安全を根本から保障できる」と発言したことがある。
強い危機意識を抱いた中国は、半導体産業において産業チェーンの強化を体系的に進めており、国産化率の向上を目指した構造への転換に取り組んでいる。そのことで、「西側に依存しないでよい底力」が徐々に形成されている。代替技術の開発の進展は目覚ましく、中国の自給率構造を徐々に変化させ、さらに世界市場において新たな競争価格と技術供給体系を生み出している。
中国が特に顕著な成果を上げている主な分野に、AI関連がある。米国によるこの分野への戦略的封鎖は限定的な効果しか発揮していない。米国はNVIDIAのハイエンドチップの規制を軸として中国の大規模モデル訓練能力を抑え込もうとしているが、中国企業は中規模演算能力、大規模データ、高効率モデルの開発を進めており、中国語の言語モデルを自主開発し、オープンソースで共有している。
中国で開発されたAIのディープシーク(DeepSeek)は中国市場で主導的地位を獲得したのみならず、多くのBRICS諸国や東南アジアの新興市場でも採用され、これらの地域で米欧のAI製品の主導的地位を脅かしている。中国企業は開放戦略を積極的に展開し、「非米国型デジタルエコシステム」の構築に取り組んでおり、対外依存を低減すると同時に、自国の基準を開発途上国や新興国に輸出することで、世界のデジタルシステムの構築での主導権の一部を徐々に獲得しつつある。ロボットや電気自動車(EV)の分野でもよく似た状況が発生している。
英「エコノミスト」誌は、米国による技術封鎖が中国に、国家体制全体の動員による技術の発展の加速を促したと指摘し、「中国はむしろ強くなるかもしれない」と強調した。
海上では、中国製の貨物船が世界の海運市場を席巻している。宇宙分野では、中国はすでに数百基の衛星を打ち上げ、地球のあらゆる場所をモニタリングしており、技術は米国に肉薄している。軍事においては戦闘機やミサイル、艦船などが米国の水準に接近している。
中国は10年前、「中国製造2025」という政策により、ロボット技術、航空宇宙、新エネルギー車(非従来型の動力を利用する自動車)など10の国家重点発展分野を定めたが、これらは現在のところほぼ目標を達成している。
1990年代、技術面で先行していた日本は貿易で圧倒的な強さを見せ、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の名を得た。中国も科学技術の発展路線で難関の突破に成功すれば、製造業製品において「チャイナ・アズ・ナンバーワン」の称号を得ることができるかもしれない。(翻訳・編集/如月隼人)
関連記事
幼児が乗るベビーカーに生きたヘビ隠す、税関で摘発―香港メディア
Record China
2025/7/4
韓国の李在明大統領が雇用労働相に戦闘的労組出身者を抜てき、保守系紙は警戒感
Record Korea
2025/7/4
米国の格付け大手が中国を「A1」に据え置き、当局者は「前向きな評価」と歓迎
Record China
2025/7/4
日本でも爆発事故……中国モバイルバッテリーメーカーが生産停止、「倒産」は否定
Record China
2025/7/4
石破首相らがNATO首脳会議欠席、「異例の集団回避は顕著な外交シグナル」と中国メディア
Record China
2025/7/4
「日本に来て中国のことがもっと好きになった」との投稿に反響=「分かる」「私は日本の方が好き」
Record China
2025/7/4