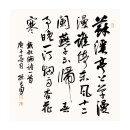「クレヨンしんちゃん」は大人に不可欠の作品、「低俗ギャグ」から「心の癒やし」に―中国メディア
拡大
9日、中国のポータルサイト・捜狐に「クレヨンしんちゃん」は大人に不可欠だとする記事が掲載された。
2025年5月9日、中国のポータルサイト・捜狐に「クレヨンしんちゃん」は大人に不可欠だとする記事が掲載された。
記事はまず、「『クレヨンしんちゃん』は、しばしば『頭を使わないギャグアニメ』として扱われがちだが、その本質は原作者・臼井儀人氏が子どもの無邪気さで包んだ大人の寓話である。表面的にはくだらなくても、その背後には現代社会への鋭い風刺が隠されているのだ。野原一家の日常には、住宅ローンの重圧、過酷な労働環境、育児ストレスといった、現代の大人が抱えるリアルな生活の苦しみが描かれている」と紹介した。
そして、「作中には子どもには理解し難いブラックユーモアが数多く含まれている。たとえば、母・みさえがこっそり隠すへそくり、父・ひろしがひそかに楽しむ水着雑誌、スーパーでの主婦同士の見栄の張り合いなどは、大人の日常そのものを映し出している。視聴者が『子どもの頃はしんちゃんを見ていたが、大人になったら自分がひろしになっていた』と語るように、『クレヨンしんちゃん』は人生の変化を映す鏡ともなっているのだ」と述べた。
続いて、「ひろしが残業のせいで娘の発表会を見逃すシーンを見た時、同情よりもむしろ安堵(あんど)する。なぜなら、自分だけでなく、世界中の働く人々が同じような苦しみを抱えていると気づくからだ。みさえは住宅ローンの支払いに嘆きつつも、通販で無駄な買い物をして気を紛らわせる。しんのすけは両親のケンカを『ケツだけ星人』のネタで茶化し、家庭内の緊張を解きほぐす。こうした完璧ではないがリアルな対処法こそ、現代人が求める感情の出口であり、心理学者が語る『もろさを認める心の癒やし』の実践形であるのだ」と論じた。
また、「しんのすけの問題児的行動は、社会の規律や束縛に対する反抗の象徴である。しんのすけは幼稚園の受験競争のプレッシャーに対して、補習よりもアクション仮面が大事だと信じて疑わない。このように、社会に飼いならされていない純粋な生命力は、大人たちにとっては道具的合理性にあらがう精神的な象徴なのである」と言及した。
さらに、「『クレヨンしんちゃん』のホラー回も実は大人の心理的危機を象徴的に描いたものである。かくれんぼで、存在しない子ども」が増えるエピソードは、職場における見えない競争やプレッシャーを象徴し、エレベーターが7階に到達できない異次元空間は、昇進の壁に直面する中年の苦悩を暗示している。さらに、仲間が次々と石像に変わる悪夢は、同世代との競争や比較の中で個性を失っていく現代人の姿を投影している。これらのホラー描写は、非現実的でありながらも、現実社会の矛盾やストレスを如実に映し出しているのだ」と説明した。
記事は、野原家について「現代日本の家庭を象徴する典型的なサンプルと言える」と言及。「ひろしは昭和の『硬派な父親像』から平成の『だめ親父』へと変容し、経済バブル崩壊後の男性像を示している。みさえもまた『完璧な主婦』という理想像の裏で、手抜き、暴食、虚栄心に悩む姿を見せる。しんのすけと祖父の関係も、年齢差を越えた友情を描き、厳格な孝道文化に一石を投じている。作中でたびたび描かれる、家族全員が閉じ込められるエピソードは、家族関係の試練として描かれ、社会規範が崩壊した状況下で、家族の絆がどのように再生されるかが問われる構造となっている」とした。
そして、「80・90年代生まれにとって、『クレヨンしんちゃん』は記憶の扉を開く鍵である。オープニングテーマが流れると、放課後にお菓子を食べながらアニメを見ていた子ども時代の情景が一気によみがえる。このように『子ども時代のフィルター』と『大人の視点』が交差することで、独特な没入感が生まれているのだ。この大人の童話の中で、私たちは人生の荒々しい現実に向き合いながらも、前に進むための不条理な勇気を見いだすことができる。『夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ』という有名な言葉には真理があるのだ」と結んだ。(翻訳・編集/岩田)
関連記事
「クレヨンしんちゃん」の笑いに隠された温かい物語―中国メディア
Record China
2025/3/23
2025年も「クレヨンしんちゃん」や「名探偵コナン」が見続けられる理由―中国メディア
Record China
2025/1/23
「クレヨンしんちゃん」は私たちの成長に寄り添い続けてくれるアニメ作品―中国メディア
Record China
2025/1/18
中国の若者が「クレヨンしんちゃん」の家を原寸大で再現、代理店も地元も応援
Record China
2025/1/1
「日本の子どもはすごい、完敗」の投稿写真に中国で驚き=「これが普通なの?」「いや完勝でしょ」
Record China
2024/12/21
「映画クレヨンしんちゃん」、平凡だが温かさや感動も味わえる作品―中国メディア
Record China
2024/12/6