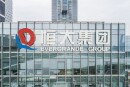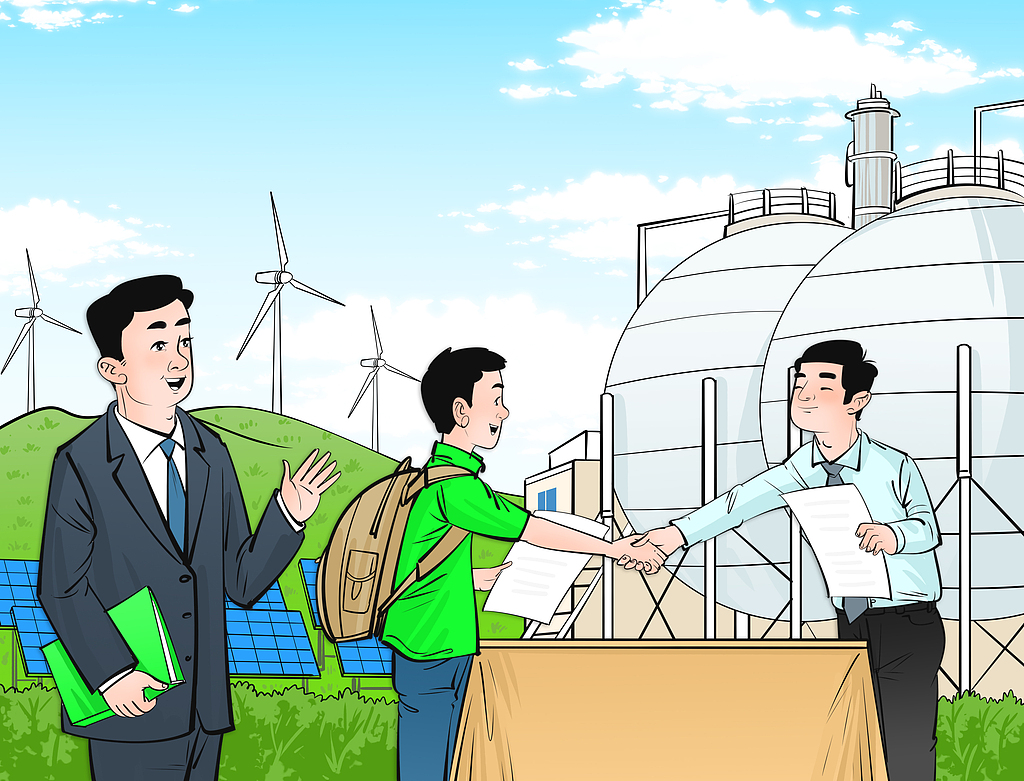常連客はカモかニラか?VIPなのに割高、ECアプリに潜む「殺熟」の真相
拡大
1杯のコーヒーが暴いた見えない価格差。「同じ商品なのにアカウントで価格が違う」という問題は、ビッグデータ時代における「殺熟=常連ほど損をする」現象の一つとみられている。
1杯のコーヒーが暴いた見えない価格差。「同じ商品なのにアカウントで価格が違う」という問題は、ビッグデータ時代における「殺熟=常連ほど損をする」現象の一つとみられている。
ラッキン騒動が映す「殺熟」の現実
発端はラッキンコーヒーのアプリを巡る小さな騒動だ。あるユーザーが同僚と同時に同じ商品を注文したところ、表示された価格に差があった。しかも高値が提示されたのは、より頻繁にアプリを利用していたユーザーのアカウントの方だった。
そんな出来事を明かした投稿はたちまちSNSで拡散され、そこで改めて「殺熟」が注目を集めた。なじみ客ほど損をする(搾取される)という中国発のネットスラングだ。
搾取は親しき人から?
通常、常連客にはポイント加算や会員特典などの優待が付与されてしかるべきと思いきや、逆に割引なしの高値が提示される。そんな電子商取引での現象が散見されたのは今に始まったことではない。アルゴリズム社会の下では、常連客になることで優待を得られるどころか、持続的にカモにされるのがオチというわけだ。
しかも一度高額グループに分類されると、その状態は続きやすい。中国語では持続的にカモにされることを「割韭菜」と呼ぶ。ニラを刈る、つまり再び生えるものだから何度でも刈られるということだ。そんな立場の存在に私たち自身が陥っている可能性は否定できない。
お得意様が狙われるのはなぜ?
中国ではこれまでも配車アプリのDiDi(滴滴出行)、美団(メイトゥアン)、携程(Ctrip)など、さまざまなデジタルプラットフォームで「殺熟」の事例が報告されてきた。
検索履歴や購入頻度、使用端末の種類などから「この人は買う気がある」と判断されると、そっと価格がつり上げられる。あたかもアルゴリズムがユーザーのアクションを追跡しつつ、カモがネギを背負ってきたと判断していると言わんばかりだ。
ちなみに同じ電子商取引のプラットフォームを使用していても、iOSユーザーの方がAndroidユーザーより高値で表示される傾向があるとした説がネットでは浸透している。「iPhone=高所得者」というイメージが値付けの根拠になっているというのだ。
公平の名を借りた不平等
中国政府は「インターネット情報サービスアルゴリズム推薦管理規定」(22年3月1日施行)に続き、「中華人民共和国消費者権益保護法施行規則」(24年7月1日施行)を定めるなど、ビッグデータを活用した常連客に対する価格の差別的待遇の問題にメスを入れてきた。
しかし、「殺熟」行為はその後も死に絶えることなく、形を変えて生き続けているかのようだ。制度の網をすり抜けるように、静かに、そしてしたたかに。「全ての消費者に対して公平な取引を保証する」ことを達成するにはまだまだ多くのハードルを越えていく必要がありそうだ。
刈られ続けるニラ
常連客は大切にされると信じてきた私たちにとって、「殺熟」はネットスラング以上の響きを持っている。話が飛躍するかもしれないが、訪日外国人(一見さん)が免税制度を利用できるのに対し、日本国内の生活者(常連客)は当然ながらその恩恵は得られない。もしかしたら、そんな構造を「ニラ刈り」の一種とみなす意見もあるかもしれない。
プラットフォームへの信頼と忠誠心に基づいた消費行動がいつの間にかカモやニラとして刈り取られる側に回るかもしれない不条理。それでも私たちは懲りずにスマートフォンをタップし続ける。賢い消費者であるためには、演出されたお得感に疑問を抱き、必要に応じて公正を求めていく覚悟が求められそうだ。(提供/邦人NAVI微信公衆号<WeChat公式アカウント>)

関連記事
ラッキンコーヒー、スマホアプリによって変わる価格設定が物議―中国
Record China
2025/5/3
韓国の飲食店を訪れた外国人、カード決済できず連れて行かれた場所は…=ネット「これが美談?」
Record Korea
2025/5/4
これが1200円?韓国の障害者スポーツ大会で弁当に批判殺到=韓国ネット「予算の横領では?」
Record Korea
2025/4/27
「日本のご近所さんはどうして…」中国人留学生の投稿に、中国ネット「愛がある」
Record China
2024/12/14
奈良公園のシカに中国から持参した菓子与える、日本人から批判殺到―台湾メディア
Record China
2024/12/12
「ちいかわ」うさぎの縫いぐるみが台湾で約8万円に高騰、ファン仰天―台湾メディア
Record China
2024/10/12