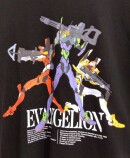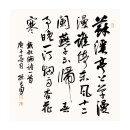寝そべり族の進化系「ネズミ人間」のサバイバル術、日本の「低欲望」とどう違う?
拡大
中国のソーシャルメディアで「ネズミ人間」が話題となっている。写真は上海の若者。
中国のソーシャルメディアで話題となっている「ネズミ人間(老鼠人)」。都市に住む若者の生存戦略として静かに広がるライフスタイルは日本の「低欲望」にも通じそうだが、大きな相違点もある。
「ネズミ人間」とは?
「ゲゲゲの鬼太郎」に登場するネズミ男は、俗っぽくてずる賢いが、どこか憎めないキャラクターとして人間社会の弱さを象徴したキャラクターとして知られる。しかし、中国のソーシャルメディアで流行中の「ネズミ人間」というネットスラングは、これとは特に関係はなさそうだ。
「ネズミ人間」は、社会の過酷な競争を回避し、都市の片隅で目立たず、低エネルギー消費をモットーとしながら巧妙に生き延びている。そんなあたかも「引きこもり」「陰キャ」にも似た(ただし相違点がある)ライフスタイルが今、中国の若者の間に浸透しているという。
寝そべり族の進化系?
「ネズミ人間」という呼称は、長期間暗い環境で過ごしている者は強い光にさらされると精神的に崩れてしまうというところから付けられた(心の防御が崩れるという意味で「破防」というネットスラングも流行した)。日本語のニュアンスから言えば、「モグラ族」と呼んだ方が理解しやすいかもしれない。
実は、「ネズミ人間」はすっかりおなじみとなった「躺平族(タンピン族、寝そべり族)」の進化系とも見られている。ただし、「躺平族」が過酷な競争社会に疲れ、受動的に撤退し「寝そべる」ことを選んでいるのに対して、「ネズミ人間」は社会の隙間に賢く入り込み、自衛的かつ戦略的に生き延びる道を模索している側面がある。
孔乙己文学、低頻、淡人
いわば「努力しても報われない」という諦観に基づいて自衛的な生き方として「ネズミ人間」のライフスタイルがあるというのだ。「孔乙己文学(高学歴でありながら報われない自分の境遇を自嘲気味に描く若者の投稿スタイル)」や「低頻人(ローフリケンシー人間)」「淡人(淡泊系人間)」などに通じるところもある。
「孔乙己文学」は学歴社会に疲弊した若者による文学的自嘲表現であり、「低頻人」はSNS利用頻度を意識的に減らし、他者との接触を避けるライフスタイルを指す。「淡人」は欲望や関心を積極的に削ぎ落とし、淡々と生きる人々を指す。断捨離やミニマリストとも通じるが、より内向的で感情の起伏が少ない傾向が指摘されている。
日本の「低欲望」との相違点
日本で1990年代に話題になった「ジベタリアン」や「無気力症候群(アパシー・シンドローム)」とも区別されそうだ。前者は社会規範からの逸脱を示す象徴として語られるものであり、後者は社会や学習への関心喪失という側面に注目した言葉だった。
むしろ、「ネズミ人間」との対比を試みるなら、大前研一氏の著書「低欲望社会」(2015年、小学館)が適当かもしれない。氏は同書で高齢化と人口減少が加速する中で欲のない若者が増えている現状を指摘し、リスクや野心を避ける「普通がいい病」の蔓延に警鐘を鳴らしていた。
欲望を取り戻せる社会へ
ただ、日本における低欲望が自主的に(過度に)欲望を放棄する現象であるのに対し、中国における「ネズミ人間」は、「996」に見られる長い労働時間(勤務時間は朝9時から夜9時まで、週6日出勤)や過剰な競争環境(内巻)に欲望を抑圧され、その結果として欲望を諦めざるを得ない状況に追い込まれる状況を背景としている。
中にはペット飼育や趣味による社交などを通じ、「ネズミ人間」から脱する力を取り戻していく若者は存在するものの、「欲望を持てない社会」が長期に及べば、経済成長や社会活力を損なう可能性が高くなる。中国でも若者が欲望や希望を持てるような雇用環境、教育制度の整備、社会評価基準の設定など根本的な制度設計の見直しが求められる時期に差し掛かっているといえそうだ。(提供/邦人NAVI微信公衆号<WeChat公式アカウント>)

関連記事
日本経済低迷の原因は「日本人の意地悪さ」に? 中国ネット「イメージ通り」「中国の若者も…」
Record China
2025/5/3
「政治的な意図」のない若者たちの行動が、中国当局にとって厄介な問題に―仏専門家
Record China
2024/12/24
「日本の孤独死」が中国のSNSで大反響=ネット民「政府の宣伝か」「死ぬ時はみんな一人」
Record China
2024/10/20
屋上で背中を焼いていた女性、死体と間違われ通報される―中国
Record China
2024/9/5
日本の若者も「寝そべる」のか?―華字メディア
Record China
2024/7/10
日本のGDP転落、「失われた何年」にはもう意味がない―香港メディア
Record China
2024/2/27