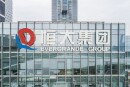中国の中高生の意外な消費観―中国メディア
拡大
中国の若者の意外な消費観について中国メディアが報じた。
中国のある女子中学生は最近、母親に「買ってほしいものリスト」を渡した。そこには衣替えシーズンで必要になった服、ペン、本、文房具などの必需品のほか、○○社のテープ5メートル、□□社のテープ7メートル、ポスター1枚…などと書かれていた。中国青年報が伝えた。
母親は「子どもが書いた買い物リストを見ても何のことかわからない時がある。娘の欲しいものを見ているとわけが分からなくなる。一体どこからこういう情報を仕入れてくるのやら…」と話している。
少し前、この女子中学生は母親に「厳粛な交渉」を申し入れ、「買い物の自由を与えて欲しい」と訴えた。しかし母親は娘の要求を拒否。「これは自由とか自由でないとかの問題ではない。ネットショッピングには危険な要素がたくさんあるのだから」と話すが、その裏には「買い物の自由を与えなければ、娘をいくらかコントロールできる」という口に出していない理由もある。
この女子中学生のリストが常軌を逸しているわけではない。最近、別の女の子で10元(約150円)出してオンラインで親友のために「彼氏」を「購入」し、母親をびっくりさせたケースがある。その後、母親がよく話を聞いてみると、10元は30分間の「バーチャル彼氏」のレンタル料金で、この30分の間に「彼氏」から親友に「宿題をするんだよ」というメッセージが何件か送られるのだという。
昨年末、騰訊(テンセント)は「00後研究報告」を発表した。それによると、9都市で3万件近いサンプルを集めた調査の結果、中学・高校生が中心の00後(2000年代生まれ)は、毎月の小遣いが平均470元(約7000円)になる。別の取材によると、都市で暮らす00後の圧倒的多数が、一定の金額の、自分で自由に使える小遣いを持っているという。
大人達が「中高生の旺盛な買い物がよくわからない」ととまどっている間に、00後たちは鮮明な特色を備えた独特の消費観を形成しつつある。
■好きなもので「神」に、中学生の買い物はプロジェクト研究のよう
ブランドのスニーカーを10数足持っている文さん(14)は、最新のナイキのバスケットシューズ「エアジョーダン」を手に入れた時、微信(WeChat)の公式アカウントで4000字近くある長い文章を発信した。この文章を読んで、文さんの両親を含む多くの人は文さんをこれまでと違った目で見るようになった。
文さんの母親の劉さんは、「息子の書いた文章を読んで、スニーカーが好きなのは単にトレンドを追いかけているのではなくて、スニーカーの研究のようなものだとわかった。友だちには『シューズの神』と呼ばれていて、靴を買う前に息子に相談する子も多い」と話した。
00後を取材する中でわかったのは、彼らが「神と呼ばれる」のを好むということだ。ちょっとやそっとでは「神」にはなれない。文さんのように、自分の好きな分野を掘り下げて研究を積み重ね、周りの人から信頼と尊敬を勝ち取らなければ「神」にはなれない。前出の女子中学生は手帳が大好きなので、手帳用のテープ類を非常によく研究して、友だちに「テープの神」と呼ばれている。別の中3の女子は漢服(漢民族の伝統衣装)が好きで、漢服のいろいろなタイプに詳しいだけでなく、質問してきた友だちに「似合うタイプの漢服」をアドバイスするなどして、同じクラスの女子から「漢服の神」と目されている。ずばり「服の神」などと呼ぶ人もいる。
■お金を使う時は実用性重視、中高生の消費はそれほど「突飛」ではない
中高生の消費を詳しくみていくと、「一気にレベルアップする」傾向がある。それでは「駆け出し」から「神になる」まで、どれくらいお金を使うのだろうか。
最初に一定の「学費」を払う必要があることは確かだ。
文さんは以前、「見た目がよい」、「よく売れている」、「履き心地がよさそう」というだけの理由で、有名ブランドのエアクッション入りスニーカーを買った。ところが学校のクロスカントリーランニングに参加した時、固い小枝か何かを踏んづけて底に穴が空いてしまい、使い物にならなくなった。
幸い、文さんは「学費」をそれほど支払わなくて済んだ。この「人生で一番後悔した消費」が、文さんのスニーカー研究への興味と闘志をかき立てた。文さんは、「靴を買う時も理性的でなければならない。私たちの年代はまだ給料をもらっていないので、靴を買うお金は親に出してもらうことになる。いい靴を見つけたら、まず研究する。研究してやっぱりいいと思ったら、次は価格が適切かどうか、両親がいいと言ってくれるかどうか考えなければならない。1000元(約1万5000円)あればほかのことに使ってもいいのに、何も靴を買う必要はないじゃないのと考える時もある」と述べた。
研究には理性が必要だ。研究することで行動はより理性的になる。
多くの専門家が、「00後はそれより上の世代と比べてより豊かな物質的生活を送っており、自分の趣味や嗜好を満足させられる条件がより備わっているといえる」と指摘する。「報告」も同じような結論を出しており、調査に回答した00後の77%が、「自分の慣れ親しんだ製品、または好きな製品により多くお金を使いたい」と答えたという。
しかしお金を使うこと、イコール多額の消費であるとは限らない。たとえば前述の女子中学生はある時、暇な時間を活用して、物入れや引き出しをひっくり返し、小さい頃よく遊んでいたシールを引っ張り出してみた。すると、ほとんどのりの消えかかった小さな紙切れが、カットしたり組み合わせたりすることで、手帳の素敵なデコレーション素材になることに気づいた。「こうやって使えばごみが宝になるだけでなく、より重要なことはお金を節約できることで、とてもよいと思う」という。
中高生は競争意識が強いと言う人は多いが、取材を通してみえてきたのは、00後の消費行動には機能性重視という理性的な特徴があることだ。両親の世代に比べ、00後はブランドをあまり気にしない。買い物をする時に、どうしても日本製品や韓国製品、米国製品でなければいやだということもない。むしろ前の世代の人々よりも中国の味があるのを好む。女子中学生は、「父は私の誕生日にいつも日本製やドイツ製の文房具をプレゼントしてくれるけれど、自分で買うとしたら(中国メーカーの)晨光を選ぶ。種類が多いし、見た目もいい。自分は細いシャー芯(シャープペンシルの芯)が好きだが、国産ブランドなら0.38ミリさらには0.35ミリの極細がすぐ見つかる」と話した。(提供/人民網日本語版・編集/KS)
関連記事
中国のパイカルメーカー、「名探偵コナン」にコラボ拒否される、理由は…
Record China
2020/4/24
中国籍の女子高生が西東京市にマスク2万枚寄贈=中国ネット「天使だ」
Record China
2020/4/27
韓国で自宅隔離免除者の新型コロナ感染が判明、例外措置の適用めぐり論争勃発
Record China
2020/4/14
日本の高校生の彼女へのお願いが中国ネットで話題に=「甘すぎる!」「こんなに堂々と…」
Record China
2020/4/8
韓国系少年が治療拒否され死亡、遺族は新型コロナと知らず―米国
Record China
2020/3/31