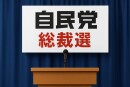中央経済政策会議3つのポイント 国内外が注目
拡大
年末が近づき、中央経済政策会議が各方面の中国経済を研究し判断する上での最も重要なバロメーターになっている。現在、国内外の機関による会議の見通しと分析は主につぎの3方面に集中している。
年末が近づき、中央経済政策会議が各方面の中国経済を研究し判断する上での最も重要なバロメーターになっている。現在、国内外の機関による会議の見通しと分析は主につぎの3方面に集中している。中国新聞社が伝えた。
増加率は重要でなくなるか?
さきに中国共産党中央政治局会議で2018年の経済活動を分析検討した際、質の高い発展を推進することが当面の、そして今後一時期の発展構想の確定、経済政策の制定、マクロコントロールの実施における根本的要求であり、認識を深め、全面的に理解し、確実に実施しなければならないことが明確に打ち出された。
クレディ・スイスの陶冬取締役社長は、「これは中国政府の経済施政の理念が重大な転換を遂げつつあり、『GDP(国内総生産)優先論』が日に日に後退し、質の向上、改革の加速、モデル転換の促進、環境保護の重視が新たな政治の立脚点になったことを示している」との見方を示す。
海通証券の姜超マクロアナリストは、「質の高い発展を推進するとは、高速発展がもはや追求する主要目標ではなくなったことを意味する」と指摘する。
JPモルガン・チェース中国法人の朱海斌チーフエコノミストは、「成長の質を強調することは、スピードがもはや一番の目標ではなくなったことを意味するが、2018年の中国が経済成長率の目標を確定しないということではない。実際、金融リスクを予防する意味でも、国民生活を保障する意味でも、ある程度の成長率を維持することは必要だ」と話す。
財政・金融政策はどうなる?
中央経済政策会議が翌年の財政政策と金融政策をどのように調整するかはこれまでずっと大きな重点だった。17年までの7年間、中国は積極的財政策と穏やかな金融政策を実施し続けてきた。
アナリストは、「2018年も中国はこの一連の政策を続けるとみられるが、『従来の政策』の背後には新しい中身が控えている」と話す。
申万宏源証券有限公司の李慧勇チーフマクロアナリストは、「社会の主要な矛盾点が転換しつつあること、貧困撲滅や汚染防止などの戦いを勝ち抜く必要があることを考えると、財政政策は貧困撲滅、環境保護、国民生活などの分野を重点的に支援するものになるだろう」と予想する。
日本のみずほ証券の沈建光チーフエコノミストは、「2018年の中国は財政政策と金融政策のバランスをより重視するようになる。一方で、財政ストックの資金をしっかり利用し、減税と料金引き下げの取り組みをしっかり行う必要がある。また一方で、税制改革、中央政府と地方政府の権限と支出責任との区分改革の歩みを加速させ、積極的な財政政策が本当に着実に実施されるようにしなければならない」と指摘する。
3つの重点課題に焦点
政治局会議の成果をみると、リスクの防止、精度の高い貧困撲滅の取り組み、汚染防止という3つの重点課題に取り組み、勝利を勝ち取ることが、今年の中央経済政策会議のキーワードになるとみられる。
沈チーフエコノミストは、「これはデレバレッジと監督管理の強化、所得分配改革、環境保護の推進が引き続き重点になることを意味する」と指摘する。
朱チーフエコノミストは、「リスク防止では次の2点に注意しなければならない。1つ目は実体経済の労働生産性をどのように引き上げ、労働生産性の低下局面を転換させるか。2つ目は金融分野のリスクをどのように着実に防止し、企業の債務を適切に処理するかだ」との見方を示す。
2018年は中国の改革開放40周年にあたり、小康社会(ややゆとりのある社会)の全面的な完成という目標を達成するための重要な年でもある。中央経済政策会議がどの改革を加速させるかという点にも、注目が集まる。
さきに政治局会議で重点活動の一部が列挙され、これには供給側構造改革の深化、農村振興戦略の実施、住宅制度改革の加速、長期的に効果を上げ得るメカニズムの構築などが含まれていた。
李チーフマクロアナリストは、「これまでの中国の供給側構造改革は過剰生産能力と在庫の削減に重点が置かれ、需給のバランスに主に取り組んでいたというなら、次の段階の改革はデレバレッジと弱点分野の補強がより注目されるようになり、質と効率の向上に主に取り組み、競争力を真に向上させると同時に財政金融リスクを引き下げるものになる。また不動産をめぐって長期的に効果を上げ得るメカニズムも18年に実質的な飛躍を遂げることが期待される」との見方を示す。(編集KS)