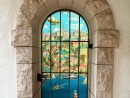日本は中国空軍の遠洋訓練に慣れるべき―中国メディア
拡大
1日、中国の専門家は、日本は中国空軍の遠洋訓練に慣れるべきだと主張している。写真は中国空軍。
(1 / 2 枚)
2015年4月1日、中国海軍軍事学術研究所の張軍社(ジャン・ジュンシャー)研究員は人民日報海外版に掲載したコラムで、日本は中国空軍の遠洋訓練に慣れるべきだと主張している。以下はその内容。
【その他の写真】
中国空軍機が先月30日、バシー海峡を通過して西太平洋で遠洋訓練を行った。空軍機は同日帰航。訓練目的を達成し、見事に任務を完了した。中国空軍のこの年度訓練計画内の通常訓練に対して、日本および一部西側メディアは魂胆ある解釈を行った。日本のメディアは、今回の訓練は中国の空軍力を近隣国に誇示するものだと主張。南シナ海情勢の緊張を激化させる可能性があると報じたメディアもあった。
こうした日本メディアの論調は彼らが長年標榜してきたいわゆる公正で客観的なイメージを示すのに無益であるのみならず、根拠も欠き、同調できないものだ。
第1に、周知のように遠洋訓練は空軍部隊の作戦能力を高める有効な方法であり、大国空軍の一致したやり方でもある。中国空軍機がバシー海峡を通過して西太平洋へ行き遠洋訓練を行うのは、国際法に完全に合致してもいる。日本の航空自衛隊の戦闘機と偵察機は西太平洋や東シナ海の上空で頻繁に活動し、米空軍の戦闘機は長年西太平洋で活動しているうえ、頻繁に「第一列島線」を通り抜けて東シナ海、南シナ海さらには朝鮮半島の上空に入って演習、訓練、偵察を行っている。日米機のこうした活動を、日本および一部西側メディアは正常なものと捉えているのに、なぜ中国空軍が西太平洋で遠洋訓練を行うことにはとやかく言うのか?こうした「役人は放火をしても許されるが、民は明かりをつけることも許されない」やり方は、彼らが中国の軍事力の正常な発展を依然色眼鏡で見ていることを物語るのみだ。
第2に、中国は海洋大国だが、まだ海洋強国ではない。歴史的に海防の弱さのためにさんざん虐げられたことは、中華民族にとって忘れがたい痛みとなった。1840年のアヘン戦争から新中国建国までの100年余りに中国は日本を含む列強による海からの侵入を470回余り受けた。現在、中国海空軍が遠洋訓練によって海上方面の防御作戦能力を高めるのは非常に必要なことであり、国家の海の安全を守るための客観的なニーズである。
第3に、中国は総合的国力の増強と国際的地位の向上に伴い、国際社会から求められる国際的な責任と義務も増え続けている。これにも同様に中国の海空軍が遠洋へ向かい、遠洋活動能力を高めることが必要だ。例えば、昨年マレーシア航空機が消息を絶った後、中国軍は海軍艦船を派遣して捜索を行ったほか、空軍機を出動して南シナ海とインド洋南部で捜索も行った。こうした行動にはパイロットの優れた遠洋飛行能力、捜索能力が必要だ。平時に遠洋訓練を強化して初めて、中国海空軍は国際的な責任や義務をしっかりと果たすことができる。
最後に、中国の軍事力の発展と中国軍の正常な演習・訓練活動を理性的に受け止めてもらいたい。近年、中国は総合国力と経済力の強化に伴い、近代化が長足の進歩を遂げているが、先進国と比べるとまだ大きな開きがある。中国が国防・軍建設を強化するのは全く正常であり、完全に主権と安全の維持のために必要なことだ。日本などの国がいわゆる「中国軍事脅威論」を再三吹聴しても、人々を納得させるのは難しい。広大な西太平洋は多くのアジア太平洋諸国の海空軍にとって天然の訓練場だ。バシー海峡、宮古海峡、大隅海峡など関係海域は各国がいずれも航行と上空通過の自由を有する区域であり、中国海空軍の艦艇や航空機がこうした海域を通過して西太平洋で訓練を行うのは、国連海洋法条約その他一般に認められた国際法の原則に合致する。関係国は中国海空軍の艦艇や航空機による同様の遠洋訓練任務に徐々に慣れるべきだ。あれこれ口出しし、世論の争点を作り出すのではないのだ。(提供/人民網日本語版・翻訳/NA・編集/武藤)
関連記事
「中国は南シナ海に“万里の長城”を作っている」、米海軍司令官が中国の岩礁埋め立て工事を批判―米メディア
Record China
2015/4/2
安倍首相の「慰安婦は人身売買」発言で大規模抗議集会、ソウルの大使館前で「性奴隷の事実から目を背けるな」―米メディア
Record China
2015/4/2
韓国型戦闘機開発事業、KAIを優先交渉事業者に選定=韓国ネットでは巨額資金の使途やステルス技術移転を疑問視する声
Record China
2015/4/2
日本とまともに戦える中国艦艇は1種類だけ、元自衛隊士官の発言に「艦艇なんて必要ない」「早く攻撃して来い」―中国ネット
Record China
2015/4/2
JYJジェジュンの兵役直前インタビュー、中国のファンに「待っていて」―中国メディア
Record China
2015/4/1